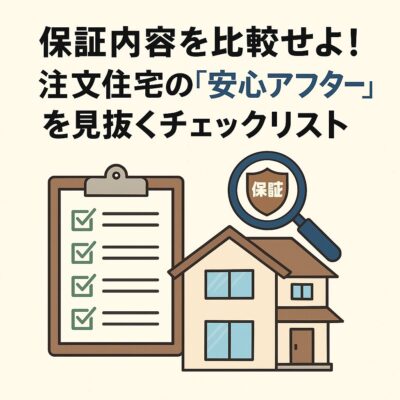
「価格は安い。でも、保証やアフターは大丈夫?」
注文住宅の資料を集めていると、どうしても“見積もり金額”に目がいきがちです。 しかし、実際に住み始めてから差が出るのが「保証内容」と「アフター対応」。
この部分を軽視してしまうと、住んでから「こんなはずじゃなかった…」と後悔するリスクが高まります。
この記事では、年収400万円台で家を建てる人が後悔しないために、各住宅会社の“保証&アフター体制”をどう比較すればよいかを、実例とチェックポイントを交えながら詳しく解説します。
1. まず理解したい「最低限の保証」=10年保証の中身
注文住宅を建てると、自動的に付帯されるのが「住宅瑕疵担保責任保険(いわゆる10年保証)」です。
これは法律で義務づけられている制度で、**構造耐力上主要な部分(柱・梁・基礎など)と、雨水の侵入を防ぐ部分(屋根・外壁など)**に限って10年間の保証が付くものです。
▶ 逆に言えば、それ以外は保証外です。給湯器・換気扇・床材・壁紙・塗装などは原則対象外です。
多くの人が「10年保証=家全体が保証される」と思いがちですが、実際には“最も重要な構造部分のみ”に限られます。 そのため、住み始めて数年後に設備が故障しても、「それは保証外ですね」と言われてしまうケースが後を絶ちません。
▶ この制度は最低限のセーフティネットであり、「安心」のすべてではない点を押さえておきましょう。
2. 各社で違う「延長保証」「独自保証」のチェックポイント
住宅会社によっては、以下のような独自の延長保証や無償点検サービスを用意していることもあります。
- 構造・防水の延長保証(20年・30年)
- 設備機器保証(5〜10年)
- 無料定期点検(5年・10年・20年など)
このような“延長サービス”が充実していると魅力的に見えますが、実際にはいくつかの条件や落とし穴があります。
- 延長には「定期点検を受けること」が条件のことが多い(未実施だと失効)
- 点検そのものは無料でも、修理対応は有料という場合も多い
- メーカー指定の部品や工事でないと保証が切れるケースも
さらに、「定期点検を断ったら、その後の延長保証が無効になった」という声もあるため、**制度の“維持条件”**までしっかり確認する必要があります。
▶ 見た目の「◯年保証」だけで判断せず、中身・条件・維持費用までトータルで比較しましょう。
3. ハウスメーカーと工務店のアフター体制の違い
保証や点検体制の差は、住宅会社の規模によっても現れます。
| 比較項目 | ハウスメーカー | 地元工務店 |
|---|---|---|
| 点検制度 | 定期点検あり(書面対応) | 任意または口頭のみの場合も |
| 履歴管理 | アプリやクラウドで管理 | 手動 or 対応なしが多い |
| 保証書の明確さ | 標準化されている | 個別対応・記載が曖昧な場合も |
| トラブル時の対応 | 専用窓口あり/24時間対応など | 代表者に直接連絡する形式 |
地元の工務店にも、“顔が見える関係”や“相談しやすさ”という強みがありますが、体制が個人任せになりやすいという側面も。
▶ 重要なのは「誰が・いつ・どんな体制で対応してくれるか」。事前に聞いておくだけで、トラブル時の安心感が全く違います。
4. 契約前に聞くべき!保証・アフター比較チェックリスト
見積もりの比較だけでなく、「保証やアフターサービスも比べる」という意識が重要です。 以下の質問を、住宅会社ごとに横並びで聞いておくと、あとから比較しやすくなります。
- 保証書はどこまで明記されていますか?(設備・構造・防水など)
- 設備機器の保証は何年ありますか?内容は部位ごとに違いますか?
- 定期点検のスケジュールは?点検費用はかかりますか?
- 保証を延長するための条件(例:定期点検の継続)は何ですか?
- 担当者が異動・退職した場合、誰が後任になりますか?
- 緊急時の連絡体制は?夜間・休日対応はありますか?
- 小修理・メンテナンスの費用はどのくらいですか?(例:網戸張り替え)
- アプリやWEBで履歴確認・依頼ができますか?
- 保証対象外になる事例として、どういうケースがありますか?(例:経年劣化)
- 保証が切れた後に入れる有料メンテナンスプランはありますか?
▶ この10項目をもとに、住宅会社ごとの対応を並べてみると、**価格だけでは見えない“安心感の差”**が浮き彫りになります。
5. まとめ|「価格」だけでなく「安心」も比較しよう
注文住宅は“建てて終わり”ではありません。むしろ、「建てたあと」の対応こそが満足度に直結します。
年収400万円台の限られた予算の中では、トラブル対応が有償になるか無償になるかで家計への影響も大きく変わります。
とくに築10年を超える頃から、住宅は劣化・修繕のフェーズに入ります。そのときに、しっかりと対応してくれる会社を選べているかどうかで、将来の安心感がまるで違います。
👉 見積もり金額だけでなく、「保証の内容」「アフターの体制」も冷静に比較し、“建てた後も安心できる家づくり”を目指しましょう。
👉 タウンライフ家づくりなどを通じて、保証体制まで含めた資料を取り寄せておくことで、「建てる前に知っておくべき違い」を明確に見抜くことができます。